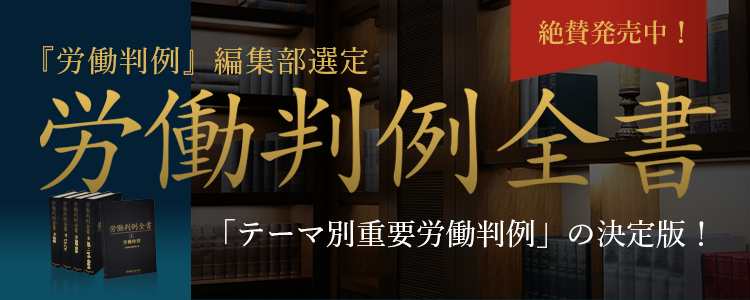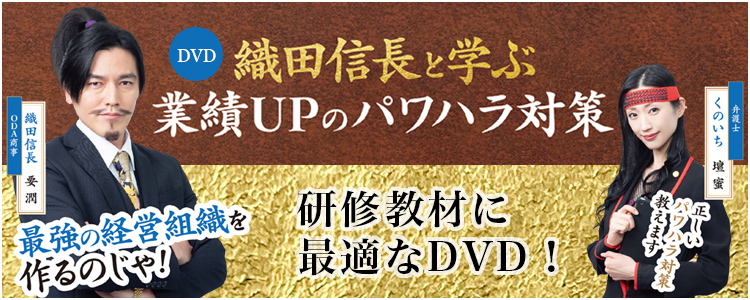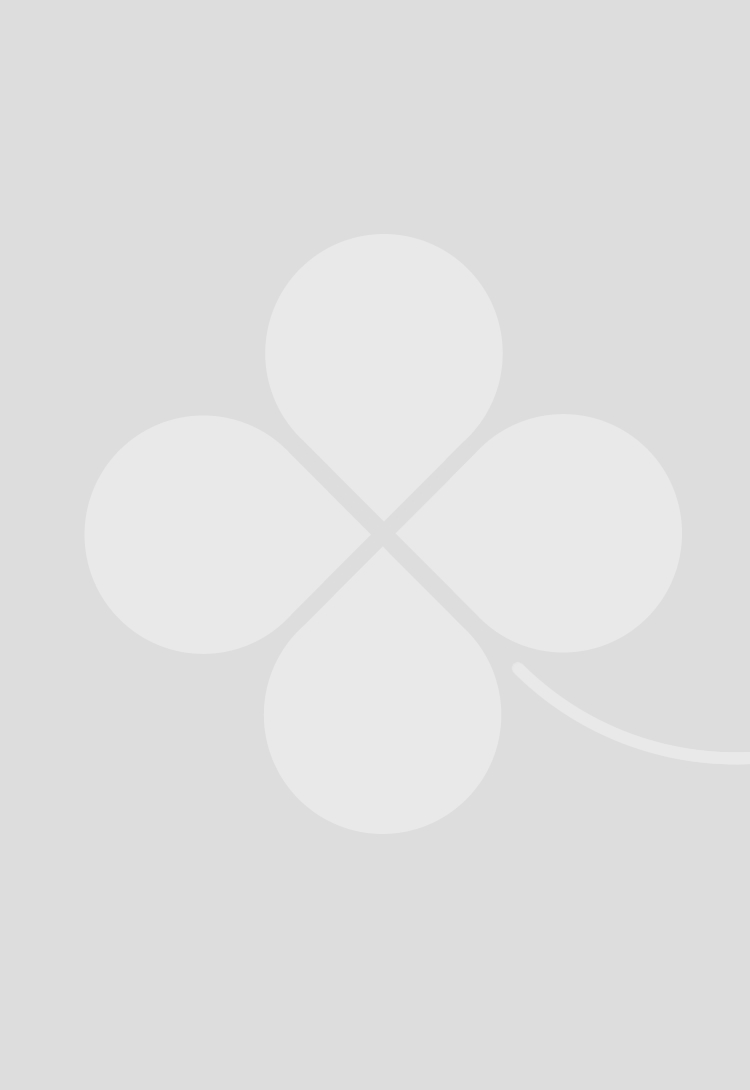企業と人材 「はたらくを楽しく」部門 優秀賞:NTTテクノクロス
First Penguin Lab事務局 福島隆寛さん/森本龍太郎さん
First Penguin Labによるチャレンジの促進
(社内実践コミュニティの創出と活動の支援)
働いていて「楽しかった」と思える瞬間はさまざまだと思いますが、「やりたいことをやれている時」をあげる人も多いのではないでしょうか。NTTテクノクロス株式会社では、2017年から、社員が自由にアイデアを出し、メンバーを集め、チャレンジする実践コミュニティ創出プラットフォーム「First Penguin Lab」を運営しています。働くことをもっと面白くするラボ活動について、事務局の福島隆寛さん、森本龍太郎さんにお話しをうかがいました。
本社 : 東京都港区
従業員数 : 1,877人(2024年3月末日現在)
事業内容 : ソフトウェア・情報通信ネットワークシステム・ハードウェアの設計、開発、販売、運用・保守、およびそれらに関わるコンサルティングなど
挑戦を積み重ねる!
「First Penguin Lab」は、社員のアイデアから生まれた実践コミュニティ「ラボ」を生み出し、そこでの活動を後押ししていくプラットフォームです。その目的は、業務ではなかなかできないような挑戦をラボ活動によって促し、未知の領域に飛び込む挑戦を積み重ねることで、イノベーティブな組織文化を創り出していくこと。この活動がスタートした背景には、NTT テクノクロスの設立経緯からくる課題認識がありました。
社名にある「テクノクロス」は、技術・ビジネス・人の3つの掛け合わせ(クロス)を意味しています。発足の目的は、NTTの研究所技術を軸とする、世の中の先端技術やサービスを掛け合わせた新たな価値を提供すること。そのため、イノベーティブな組織文化の醸成が求められていました。
同社は、合併後の組織について、ダニエル・キム氏が提唱する「成功循環モデル」をもとに「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」を分析しました。すでにフラットな関係性や助け合いの文化が根づいていたことから「関係の質」は良好であったため、そこを土台に、「思考の質」「行動の質」「結果の質」をより高めていくための方法を考えるなかで出てきたのが、実践コミュニティという案です。
異なるバックグラウンドやスキル、さまざまな興味関心をもつ人材が社内で交流し、掛け合わされていくことで「思考の質」が高まり、それが「行動の質」や「結果の質」にもつながっていくのではないかと考えたそうです。
福島さんは、「自らの興味関心を源泉とする行動は、自ずと熱を帯びます。それを支援して、行動を積み重ねていくことで、会社が目指すイノベーティブな組織文化の醸成につながっていくのではないかという仮説を立て、実践コミュニティを生み出すためのプラットフォームとして『First Penguin Lab』を立ち上げました」と話します。
自由な挑戦を後押し!
ラボは、社員の自発的な興味関心によるボトムアップ活動であり、「こんなことをやってみたい」と思えば、誰でもいつでもラボを起こすことができます。やってみたい内容を事務局に口頭でもチャットでも連絡すれば OK で、挑戦を見える化していこうという点以外は条件を設けておらず、審査もありません。月次や週次などの細かい進捗報告も必要ありません。自由度が高いのもラボの特徴です。
ラボ設立の経緯としては、大きくは、本人の興味関心からはじまるケースと、後述する社内ワークシ ョップなどでの話し合いからはじまるケースに分かれるそうです。
ラボ設立後は、興味をもった社員が加入したり、必要なスキルをもつ人を勧誘するなどして活動を進めていきます。開始当初は、ラボ数は5つ、参加者も20人ほどでしたが、今では、通算のラボ数は30以上、参加者も100人以上になっているそうです。
このなかで、事務局の主な役割は、「First Penguin Lab」を運営していくことで、新規ラボ設立の促進、各ラボの活動を支援・伴走していくことになります。First Penguin Lab は全社横断のバーチャル組織のようなものなので、必要に応じて、経営層や人事、総務、広報などの部門と連携しながら、また、場合によっては、他社や大学、社外有識者とも連携しながら、活動を支えていきます。
事務局では、スタート時から、①社員の自主的な活動を尊重する、②事務局が支援する、③勤務時間内の活動を可能とする、④プロセスを重視する、という4点を大切にしてきました。
このうち③については、「会社の施策であるため、業務中に活動して OK」と伝えています。そうすることで、育児中など、時間に制限のある社員も参加しやすくなっているそうです。毎年予算も確保しており、First Penguin Lab はボトムアップでありつつ、トップダウンのよいところをあわせもった活動となっています。
最もFirst Penguinなラボを表彰!
ラボ活動は、7月からの1年間を「1シーズン」として進めていきます。
7月に、そのシーズンのキックオフを実施します。ここでは、First Penguin Lab のシーズン計画なども公開しています。その後は、ラボごとに自由に活動を続け、中間となる12月に「活動発表会」を、翌年7月に「First Penguin Lab Awards」を開催しています。
Awards は、最も「First Penguin」を体現しているラボを表彰するものです。具体的には、各ラボが経営層や社員に向けて1年間の活動内容を報告し、それに対して聴講者が「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」を切り口にした評価項目で評価。その結果をもとに選考委員会が選考し、最も「First Penguin」を体現しているラボを「First Penguin賞」として表彰します。これまでに、社内外の人脈形成やアプリ開発を目的とした「esports ラボ」、介護に関する情報交換やセミナーなどを行う「介護ラボ」などが First Penguin 賞を受賞しています。
このほかシーズン中には、各ラボや事務局が主催するさまざまなイベントやワークショップが開催されています。イベントやワークショップには、ラボに入っていない社員も参加可能です。事務局では、ラボ活動をはじめるきっかけづくりとして、「会社ではできなさそうなこと」を探す「ヤバいアイデアワークショップ」を定期的に開催しているそうです。
また、毎年2月頃には、事務局主催の外部有識者による講演会も開催しています。この講演会は最新の知見や社会情勢を知る場にもなっており、2024年は、約250人の社員が参加したといいます。
実践と目的交流型のラボ活動
これまで First Penguin Lab から生まれたラボを振り返ってみると、大きく2つに分けられます。学術的な定義とは若干異なりますが、事務局では「実践コミュニティ系」と「目的交流型サードプレイス系」と呼んでいます。一つのラボで両方の側面をもつラボもあります。
実践コミュニティ系のラボは、アプリの開発や施策など、新しく何かを生み出すことを主な目的としたものとなります。2023年には、気象情報などをもとに虹の発生予報を検出する「虹予報ラボ」が立ち上がりました。
虹予報ラボ設立の経緯について、森本さんは、「『虹予報ラボ』は、2023年に開催した『ヤバいアイデアワークショップ』の話し合いがきっかけとなって立ち上がりました。ワークのなかで、『虹を見つけると嬉しい』『そういえば、最近虹を見ていない』という話が出たことから『虹をきっかけにした社員の交流機会をつくることができたら面白いのでは』となり、ラボが設立されたのです」と説明します。
虹予報ラボでは、予報アプリを開発し、社内サービスとして提供も開始しました。実際に、アプリの予報どおりに虹が出現したこともあり、その時には社内チャット上に「虹出現情報」が飛び交ったといいます。
一方、目的交流型サードプレイス系のラボは、存在することが重要なものです。先述した「介護ラボ」や「育児ラボ」「ALLY ラボ」などは、この系統に入ります。こうしたラボでは、明確な成果物を求めるよりも、そうした場が社内にあることで、社員の満足度向上や支えとなることが目的となるものが多いようです。
「今では、育児・介護中の社員や障がいをもつ社員など、いろいろな人がラボに参加してくれています。中途採用者が、前職で携わっていた業務に関するテーマをラボに持ち込むこともあります」(森本さん)
このほか、目的交流型サードプレイス系のラボには、興味や趣味で社員をつなげているものもあります。その一つが、ゲームを通じたタテ・ヨコ・ナナメの関係性構築をねらいとしてはじまった「esports ラボ」です。同社にはゲームが好きな社員が多く、esports ラボが定期的に開催している社内大会には、社長から新入社員まで1,000人以上が参加することもあるそうです。

地道に参加者を勧誘?
First Penguin Lab を運営していくうえで福島さん、森本さんが最も重視しているのが、先にあげた4つのうちの「①社員の自主的な活動を尊重する」ことです。これは、ラボ活動による「挑戦」は、自身の興味関心のもと「前のめり」になることから生まれると考えているからです。
「ラボのメンバーから相談がくれば、アドバイスをするなど必要な支援はしますが、基本は、各ラボの自主性に任せています。以前、ラボ活動を円滑に進めていくためにマニュアルのようなものを作成して配布してはどうかという案が出たことがあるのですが、『型』にはめてしまうと面白いものが生まれなくなるので作成せず、対話を通して進めるようにしています。First Penguin Lab を続けていくうえで大事なのは、『ゆるさ』をどう設計していくかだと思っているので、絶妙なゆるさで運営していけるように気をつけています」(福島さん)
一方で、ラボのようなボトムアップ活動では、時間が経つにつれてモチベーションが続かず、結果、活動自体が終了してしまうことも多々あります。 First Penguin Lab でも、スタート時は「何か面白いことができるのでは」といった期待感から詳細を説明しなくてもメンバーが集まってきていたそうですが、新規参加者数の伸び悩みといった課題が出てきました。
そこで、現在は、社内サイトでの広報などとあわせて、社員のラボへの「勧誘」も積極的に行っています。
福島さんは、基本は毎日出社して、社内で会った人に「最近何か面白いことやってる? よかったらラボつくらない?」と声を掛けているそうです。「社員のところにこまめに顔を見せに行って、『福島が来たら First Penguin Lab の話になる』というイメ ージを刷り込んでいくことで、First Penguin Labへの関心を少しでも高めていけたらと思っています」と笑います。
このほか、活動内容に対して経営層や社外有識者からポジティブなフィードバックがもらえる場を定期的に設けるといったことも行っています。First Penguin Lab をよりよくするため、事務局メンバ ーもラボを立ち上げたり、他のラボにメンバーとして参加し、ラボ活動中に感じる困難さや不便さを実際に体感し、さまざまなノウハウを蓄積しています。
イノベーティブな組織文化へ!
First Penguin Lab は、2024年7月 か ら8シーズン目に入りました。Awards で実施している成功循環モデルによる評価をみると、複数年継続して活動を続けているラボは、「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」のいずれも上昇していたそうです。
先にあげた虹予報アプリなど、実際に社内提供まで進んだ活動もありますが、事務局としては、特に成果や商品化などにはこだわっていません。成果に対する意識が強くなりすぎると、大胆な挑戦がねらいにくくなるからです。それよりも、プロセス自体を重視しながら、「ラボは、チャレンジや失敗を歓迎している」というメッセージを伝え続けることで、より多くの社員の挑戦を促していきたいと考えています。
そこに向けて事務局でも、新たな展開を検討中だといいます。
「『楽しい』と感じてもらうことが、挑戦を支える一番のモチベーションになります。そこを重視する姿勢は変わりませんが、今後は、それとあわせて、組織の創造性を高めていくことにも焦点をあてていきたいと思っています。今、あらためて、First Penguin Lab やラボ活動の意義のバージョンアップを検討しているところです」(森本さん)
「今後、ラボのあり方や活動内容が変わることがあったとしても、スタート時から大切にしている4つは守っていきたい。First Penguin Lab を通じて自発的な挑戦を広めていき、挑戦することがあたり前になる、そんなイノベーティブな組織文化をつく っていきたいですね」(福島さん)
 こんな方に
こんな方に
- 企業・団体等の
経営層 - 企業・団体等の
教育研修担当者 - 労働組合
- 教育研修
サービス提供者
- 豊富な先進企業事例を掲載
- 1テーマに複数事例を取り上げ、先進企業の取組の考え方と具体的な実施方法を理解できます
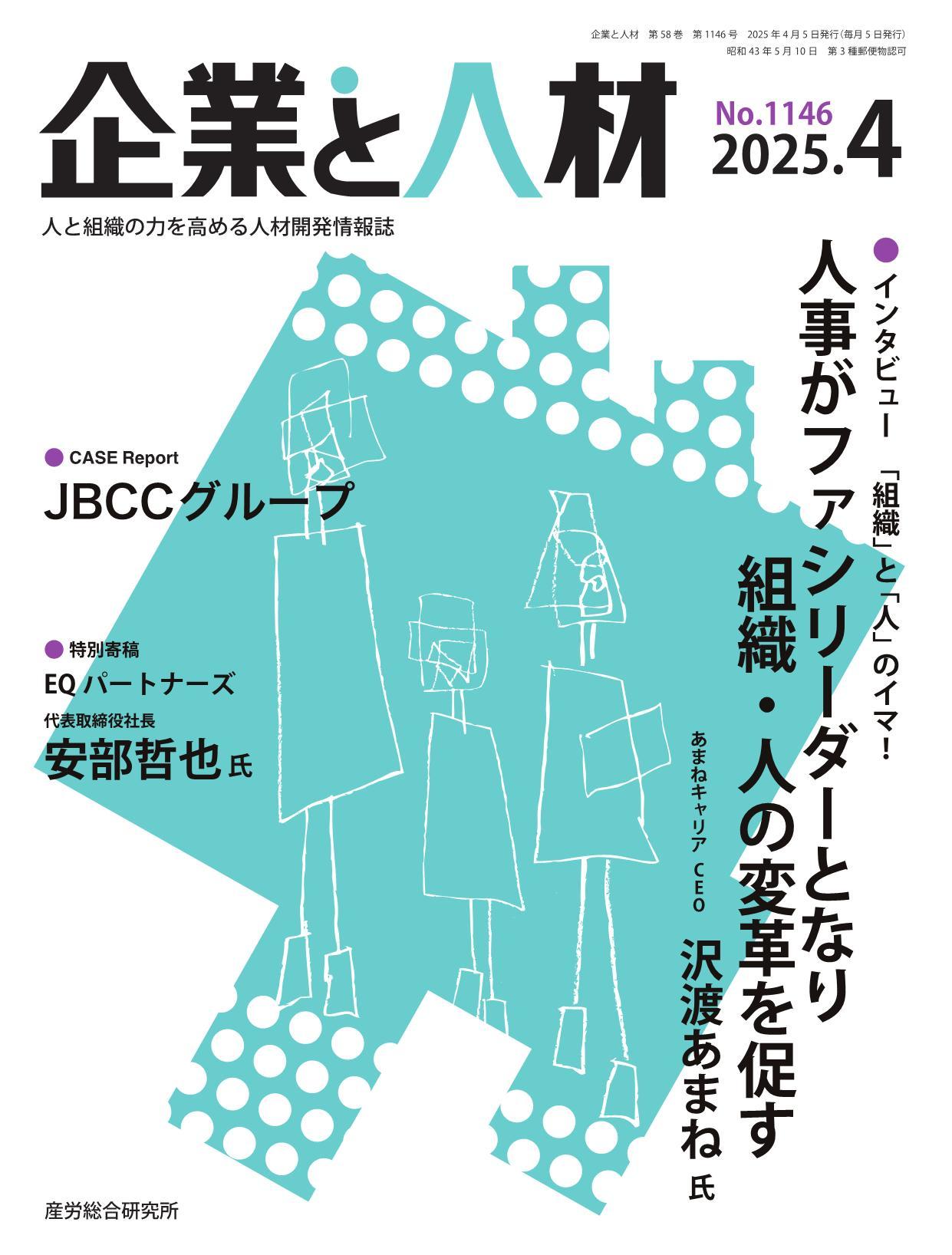 詳細を見る
詳細を見る