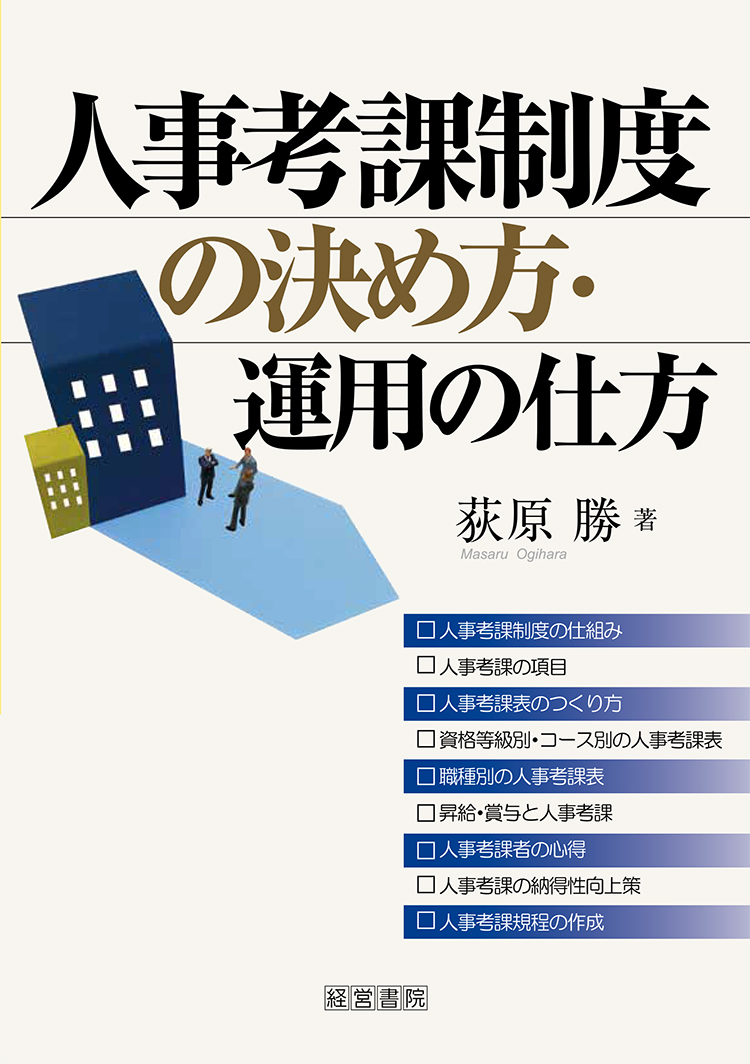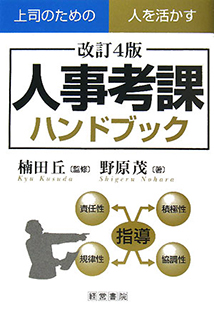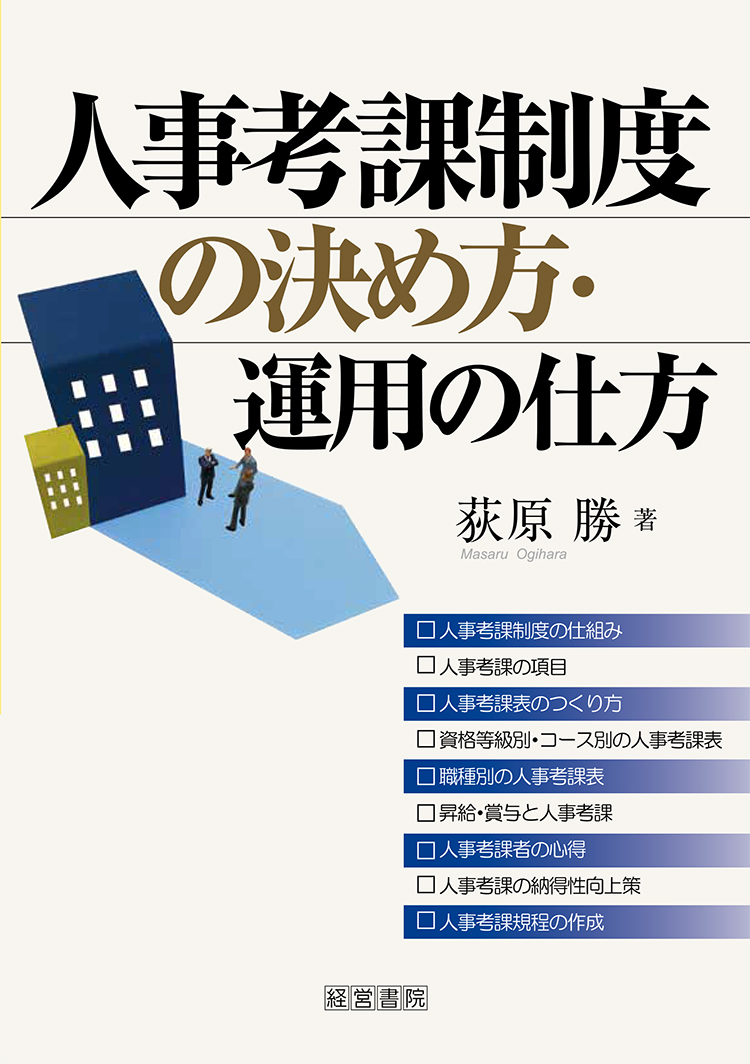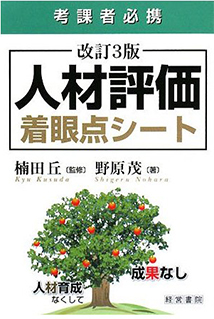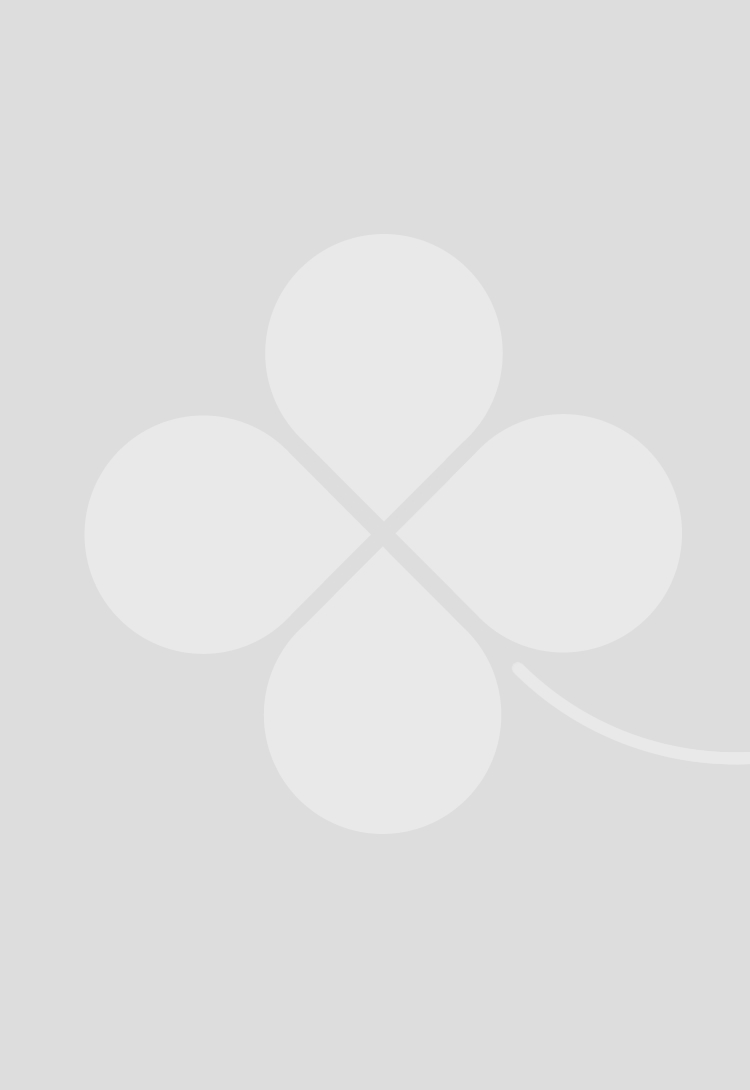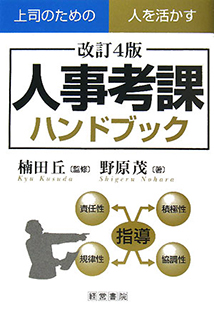まえがき
人事考課に関する、優れた専門書や解説書は、数多く出版されているとはいうものの、それはどちらかといえば、人事業務に携わる人たちを対象に書かれたものが多く、また、たまたま、現場の管理監督者向きのものがあっても、表現が固かったりして、もう一つ、気軽になじめそうもないフシが見受けられます。
人事考課において、いちばん重要な役割を果たす人たちはだれかということになると、それは人事担当部門の部長さん、課長さん、係長さんでもなければ担当者でもない。実際に工場で生産を担当したり、営業活動に従事している職場の部長さん、課長さん、係長さん、主任さん、班長さんを真っ先にあげなければならないかと思います。
人事考課の運用のカギを握っているのは、人事担当部門の人たちではなく、それぞれの部門や、職場で部下の考課に当たっている考課者、すなわち管理監督者その人です。
どこに出しても、はずかしくないだけのシステムとしてのかたちが整えられていたとしても、実際に企業や組織の中で、考課に当たる人たちが、人事考課について正しく認識し、正しく考課することをしなければ、とてもわが社の人事考課は優れたものとはいえません。
人事考課が正しく行われない場合、いちばん困るのは管理監督者自身です。それによって、部下のやる気を喪失せしめたり、職場の人間関係をまずくし、生産性を低下させたりするからです。
さらにそれによって、最も被害をこうむるのは、その企業であり組織です。
そして、最も不幸な思いをするのは、管理監督者と一緒に仕事をしている部下たちです。それは、この人たちから、“やりがい”“生きがい”を奪い去ってしまうからです。
もちろん、そうあってはならないし、またそうならないようにするため、みなさん一生懸命努力し、慎重に考課に取り組んでいることとは思いますが、その一方では、人事考課を実施する時期になると頭を痛めたり、めいった気持ちになる管理監督者が、かなりいることも事実のようです。
そこで、第一線の管理監督者の方々が、自信をもって考課に臨めるよう、また、そのためのフォローに努力されているスタッフの方のお手伝いができればという思いをこめて、本書を執筆することにしました。
本書の内容は、各企業の考課者訓練のお手伝いをするかたわら、各企業の人事考課の実態の中から、把握した問題点を整理し、それを解決するいくつかの糸口になるようにとりまとめました。
本書によって、管理監督者の方々のそして人事スタッフの肩の荷が少しでも軽くなればと念じております。
次に本書をよりよくご理解いただくため、本書をとりまとめるに当たって心がけたこと、および本書の活用方法について、念のためにしたためておきます。
本書をまとめるに当たって心がけたこと
1.人事考課と、日常のマネジメント活動を極力関連づけて説明するようにしました。
日常の部下管理と人事考課との関連、人事考課により積極的に取り組むことが、日常の部下管理にどのような効果をもたらすかなどについて、強調することに力点を置きました。
2.人事考課の仕組みやルールについて、理解しやすいように言葉や表現方法を選びました。通勤の乗物の中や、会社の休憩時間に、気軽に読んでいただけるよう努力したつもりです。
本書の活用法について
1.ハンドブック、またはマニュアルとして活用していただけるようになっています。
本書をお読みいただく過程で、“わが社の場合は、こういうことも必要だ”、“わが社の場合は、これをつけ加えておいたほうがよい”といったものがありましたら、どうかそれを空白や空欄に記入しておいてください。
2.管理監督者訓練や、考課者訓練のテキスト、サブ・テキスト、参考書としても十分に活用していただけるように工夫しました。
拙著、前著「人材評価着眼点シート」(経営書院刊)と併読していただくとなお効果的です。
本書が、人事考課にかかわる方々のお役に少しても立てば、こんな喜ばしいことはありません。
なお、本書は楠田理論をベースに著者の考えをまとめたものです。前著に引き続き恩師楠田丘先生には監修をお願いしました。深甚の意を表する次第です。