人事
賃金・賞与・退職金
人事
賃金・賞与・退職金
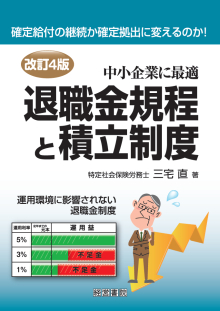 |
退職金制度はバブル経済崩壊以降泥沼のデフレ経済に陥り、従来の退職金制度を維持することは、企業の財政面における大きな企業リスクとなることが明らかになりました。今、まさに必要な退職金制度の抜本的見直しとは人事面での効果を求めながら財政面でのリスクを最小限に抑える制度を構築することです。経済や運用環境は好転もすれば悪化もします。一喜一憂しないで将来に向かって維持継続できる新しい退職金制度を構築することが急務です。本書は、これからの退職金制度を導入する際、または既存の退職金制度を見直しする際、「人事」と「財務」の2つの側面に留意しながら、何を把握し、何に注意し、どのような工程を経て行うべきかを解説しています。 ■三宅 直・著 |
本書は、これから退職金制度を導入する際、または既存の退職金制度見直しをする際、「人事」と「財務」の2つの側面に留意しながら、何を把握し、何に注意し、どのような行程を経て行うべきかを基本的解説書として表したものです。
退職金制度の変遷を見ると、まず敗戦後から昭和30年代にかけては、大企業を中心に退職一時金制度として整備されていましたが、中小企業の場合、制度として確立したものを持つところはほとんどありませんでした。
日本経済が昭和30年代から高度経済成長期に突入していくなかで、次第に国民生活にも多少の余裕が感じられるようになり、この頃より老後の生活保障を充実させる政策が次々に打ち出されてきました。公的保障としては、昭和36年に国民年金制度が創設され、形の上では国民皆年金が達成されています。
このような状況の中で、退職金においても退職一時金の年金支払い化や中小企業への退職金制度の普及政策がすすめられ、その結果、厚生年金基金、税制適格退職年金といった企業年金や中小企業退職金共済、特定退職金共済などの共済制度が誕生しました。これらは、企業に税制上の優遇措置を与えることで、安定した退職金原資の確保を促すとともに、労働者の受給権確保を目的とするものでした。
これらの制度は、高度経済成長期の真っ最中に誕生しただけに、予定される運用利率を5%以上(この当時の法定利率は年5%とされており、この為、中小企業退職金制度6%、厚生年金基金の代行部分5.5%、税制適格企業年金はほとんど5.5%以上)に設定されていました。つまり、毎年5%以上の運用ができることを前提にして制度設計がされていたわけです。
高度成長の後半期(昭和45年~50年)になり賃金水準が春闘(毎年春先に行われる労働組合による賃上げ闘争)の影響で急上昇し、それに連動して退職金支給水準が大きく上昇(私は、これを第1次退職金ショックと呼び、第1章で解説しています)した時期がありましたが、退職金積立金の運用面には何ら問題なく、運用利率5%以上という設定は「至極当たり前の常識」でした。
しかしながら、平成に入りバブル経済がはじけると同時に日本経済は、「失われた10年」、「失われた20年」といった言葉に代表される閉塞感漂う状況になっていきました。その間、日本経済は「泥沼のデフレ経済」に陥るとともに円高、株安、低金利などは当たり前のこととなり、その後のリーマン・ショック、度重なる政権交代、ユーロ危機等、様々な要因も重なって、先行きの見えない危機的状況が続いていたといえます。
このような状況の中で企業年金は、運用難により莫大な積立不足を生じさせ、また中小企業退職金共済も累積欠損を発生させ、予定利回りの引き下げを余儀なくされました。将に運用利率5%は、日本経済が右肩上がりに成長し続ける中での常識であり、低成長やマイナス成長の時代においては非常識どころか「夢物語」でしかなくなったのです。
このことは、従来の退職金制度に大きな企業リスクが潜在することを認識させ、昭和時代の高度成長期や安定成長期に導入された退職金制度をそのまま維持運営することにレッドカードを突きつけました。
そして、従来の退職金制度を維持することは、企業の財務面における大きな企業リスクとなることが明らかになりました。これは、将に退職金制度の大変革の必要性を意味するものです。私は、本文の中でも指摘していますが、この大変革期を第2次退職金ショックと呼んでいます。
ただ、この第2次退職金ショックは、厚生年金基金や税制適格退職年金などの積立不足がクローズアップされたことにより、あたかも企業年金だけの問題であるかのように受け取られてしまった向きがあります。しかしながら、第2次退職金ショックは、あらゆる退職金原資の運用状況悪化や制度の形態に原因がありました。それならば、当然、第2次退職金ショックは、ほとんどの中小企業が影響を受けている問題です。単に、企業年金を導入していた企業だけの問題ではありません。
にもかかわらず、この間に退職金制度の抜本的見直しを断行した中小企業は、どれくらい存在するでしょうか?ほんの一部分、極々僅かな数でしかありません。廃止された税制適格退職年金を契約していた企業ですら制度廃止時に積立金の社員への分配、中退共などの他制度移管といった処理は出来ていても、全体的、且つ抜本的な制度見直しは全くしておらず、積立手段が変わっただけで旧態依然の制度を維持しているケースがほとんどです。
私は、このことに本書を以って大きな警告を発します。何故なら、従来の認識や発想でこれからの退職金制度を維持することは企業経営に計り知れないリスクを生じさせるからです。
勿論、退職金の計算方法を変更した企業はあるでしょう。しかしながら計算方法の変更は、賃金制度の見直しといった人事面だけの対応であり、財務面にはほとんど影響を与えません。今、まさに必要な退職金制度の抜本的見直しとは、人事面での効果を求めながら財務面でのリスクを最小限に抑える制度を構築することです。
経済や運用環境は好転もすれば悪化もします。その都度、一喜一憂しないで将来に向かって維持継続できる新しい退職金制度を構築することが急務です。このことも「失われた20年」が我々に教えてくれた教訓ではないでしょうか。
第1章では、退職金が抱えている多くの問題点について、その変遷を説明しながら解説していきます。特に現在の退職金に関わる諸問題を第2次退職金ショックとして捉え、従来の退職金制度からの脱却を進言します。
第2章では、退職金制度が「退職金規程」と「退職金積立制度」の2つのパーツから成り立っているということ、この2つのパーツは「主従関係」にあるということを理解していただきます。この関係をしっかりと認識することが、何よりも重要なことです。
第3章では、「退職金規程」とはどのようなものか、何故この規程が重要なのか5つの重要項目を中心に説明していきます。
第4章では、退職金原資を準備する為に、どのような積立制度(手段)があるのか、主な退職金積立制度(手段)を解説しながらみていきます。
第5章では、退職金制度を新たに設計、または見直す際に知識として必要な前提条件について説明します。
第6章では、退職金制度見直しの各行程を説明します。これにより誰にも頼ることなく企業が独自で、今後も維持継続が可能な退職金制度見直しを推し進めることができるようになっています。
最後に第7章において退職金制度と税・社会保険料について説明します。
皆さまのお役にたてれば幸いです。
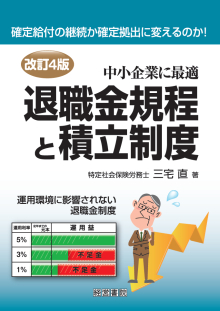 |
退職金制度はバブル経済崩壊以降泥沼のデフレ経済に陥り、従来の退職金制度を維持することは、企業の財政面における大きな企業リスクとなることが明らかになりました。今、まさに必要な退職金制度の抜本的見直しとは人事面での効果を求めながら財政面でのリスクを最小限に抑える制度を構築することです。経済や運用環境は好転もすれば悪化もします。一喜一憂しないで将来に向かって維持継続できる新しい退職金制度を構築することが急務です。本書は、これからの退職金制度を導入する際、または既存の退職金制度を見直しする際、「人事」と「財務」の2つの側面に留意しながら、何を把握し、何に注意し、どのような工程を経て行うべきかを解説しています。 ■三宅 直・著 |